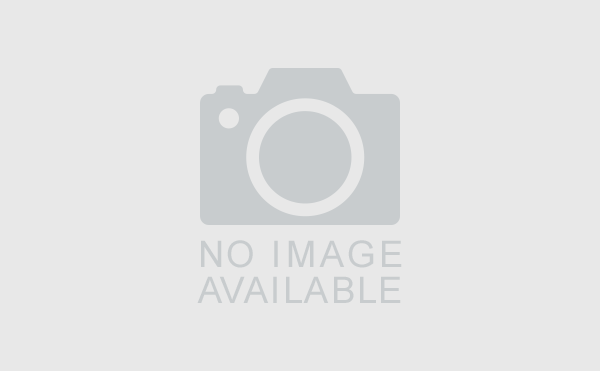令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表(厚労省)
厚生労働省は、過重な業務が原因で発生する脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病する精神障害に関する労災補償状況について、令和6年度の集計結果を公表しました。(令和7年6月25日付)
ここでは、過重な業務による脳・心臓疾患や強いストレスによる精神障害の労災請求件数と支給決定件数が詳細に報告されています。特に、業種別、職種別、年齢別、時間外労働時間別の傾向が示されており、精神障害についてはパワーハラスメントなどの「出来事」が原因となるケースが多いことが分かります。また、裁量労働制対象者や複数業務要因災害に関する状況もまとめられています。この報告は単なる数字リストではなく、今の日本の働き方のリアルな現状が映し出されています。今回はこの集計結果から日本の労働環境下で、今何が起きているのかを詳しく読み解いて行きます。
1.概要
「過労死等」とは、過労死等防止対策推進法第2条で「業務における過重な負荷による脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因とする死亡若しくは業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患若しくは精神障害をいう。」と定義されています。 本報告書は、労災請求件数、労災保険給付の支給決定件数を中心に分析しています。
2.全体的な傾向
・請求件数: 4,810件(前年度比212件増加)
・決定件数: 4,312件(前年度比1,033件増加)
・支給決定件数: 1,304件(前年度比196件増加)
※うち死亡・自殺(未遂を含む)件数: 159件(前年度比21件増加)
全体として、過労死等に関する労災請求件数、決定件数、支給決定件数はいずれも前年度から増加しています。特に、支給決定件数における死亡・自殺(未遂を含む)の増加は、過労による深刻な事態が依然として続いていることを示しています。
3. 業務災害に係る脳・心臓疾患に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数と支給決定件数
・請求件数: 1,030件(前年度比7件増加)
・うち死亡件数: 255件(前年度比8件増加)
・支給決定件数: 241件(前年度比25件増加)
※うち死亡件数: 67件(前年度比9件増加) 脳・心臓疾患による労災請求・支給決定は、件数自体は精神障害に比べて少ないものの、死亡に至るケースが多い傾向が見られます。
(2) 業種別の傾向
・請求件数が多い業種: 「運輸業、郵便業」(213件)、「卸売業、小売業」(150件)、「建設業」(128件)の順。
・支給決定件数が多い業種: 「運輸業、郵便業」(88件)、「宿泊業、飲食サービス業」(28件)、「製造業」(24件)の順。
※特記事項: 業種別(中分類)では、「運輸業、郵便業」内の「道路貨物運送業」が請求件数(155件)と支給決定件数(76件)ともに最多となっています。
(3) 職種別の傾向
・請求件数が多い職種: 「輸送・機械運転従事者」(177件)、「専門的・技術的職業従事者」(149件)、「サービス職業従事者」(136件)の順。
・支給決定件数が多い職種: 「輸送・機械運転従事者」(75件)、「サービス職業従事者」(34件)、「専門的・技術的職業従事者」(32件)の順。
※特記事項: 職種別(中分類)では、「輸送・機械運転従事者」内の「自動車運転従事者」が請求件数(163件)と支給決定件数(72件)ともに最多となっています。
(4) 年齢別の傾向
・請求件数が多い年齢層: 「50~59歳」(411件)、「60歳以上」(348件)、「40~49歳」(213件)の順。
・支給決定件数が多い年齢層: 「50~59歳」(129件)、「40~49歳」(60件)、「60歳以上」(44件)の順。
※中高年層、特に50代での請求・支給決定件数が多いことがわかります。
(5) 時間外労働時間別の傾向
・1か月評価期間の支給決定件数: 「100時間以上~120時間未満」が18件で最も多い。
・2~6か月における1か月平均評価期間の支給決定件数: 「80時間以上~100時間未満」が63件で最も多い。
これは、過労死ラインとされる月80時間以上の時間外労働が、脳・心臓疾患の発症に強く関連していることを示唆しています。
4. 業務災害に係る精神障害に関する事案の労災補償状況
(1) 請求件数と支給決定件数
・請求件数: 3,780件(前年度比205件増加)
※うち未遂を含む自殺件数: 202件(前年度比10件減少)
・支給決定件数: 1,055件(前年度比172件増加)
※うち未遂を含む自殺件数: 88件(前年度比9件増加)
精神障害に関する労災請求件数は脳・心臓疾患を大きく上回っており、支給決定件数も増加傾向にあります。
自殺件数は請求件数では減少していますが、支給決定件数では増加している点に注目が必要です。
(2) 業種別の傾向
・請求件数が多い業種: 「医療、福祉」(983件)、「製造業」(583件)、「卸売業、小売業」(545件)の順。
・支給決定件数が多い業種: 「医療、福祉」(270件)、「製造業」(161件)、「卸売業、小売業」(120件)の順。
※特記事項: 業種別(中分類)では、「医療、福祉」内の「社会保険・社会福祉・介護事業」が請求件数(589件)と支給決定件数(152件)ともに最多となっています。
(3) 職種別の傾向
・請求件数が多い職種: 「専門的・技術的職業従事者」(1,030件)、「事務従事者」(796件)、「サービス職業従事者」(556件)の順。
・支給決定件数が多い職種: 「専門的・技術的職業従事者」(300件)、「サービス職業従事者」(182件)、「事務従事者」(160件)の順。
※特記事項: 職種別(中分類)では、「事務従事者」内の「一般事務従事者」が請求件数(577件)と支給決定件数(97件)ともに最多となっています。
(4) 年齢別の傾向
・請求件数が多い年齢層: 「40~49歳」(1,041件)、「30~39歳」(889件)、「50~59歳」(870件)の順。
・支給決定件数が多い年齢層: 「40~49歳」(283件)、「30~39歳」(245件)、「20~29歳」(243件)の順。
精神障害では、脳・心臓疾患に比べて若年層からの請求・支給決定件数が多い傾向が見られます。
(5) 時間外労働時間別の傾向
1か月平均の支給決定件数: 「100時間以上~120時間未満」が74件で最も多く、次いで「40時間以上~60時間未満」が70件。
精神障害の発病においては、長時間労働だけでなく、比較的短い時間外労働でも発病に至るケースが少なくないことが示唆されます。
(6) 出来事(心理的負荷の原因)別の傾向
支給決定件数が多かった「出来事」は以下の通りです。
・「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」: 224件(最多)
・「仕事内容・仕事量の大きな変化を生じさせる出来事があった」: 119件
・「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた」: 108件
これらの結果は、職場におけるハラスメントや業務内容・量の急激な変化、顧客等からのクレームが精神障害の発病に大きな影響を与えていることを明確に示しています。
5. 複数業務要因災害に関する労災補償状況
複数業務要因災害とは、「事業主が同一でない二以上の事業に同時に使用されている労働者について、全ての就業先での業務上の負荷を総合的に評価することにより傷病等との間に因果関係が認められる災害」を指します。
・脳・心臓疾患の支給決定件数: 6件(前年度比1件増加)
※うち死亡件数: 3件(前年度比2件増加)
・精神障害の支給決定件数: 2件(前年度比2件減少)
※うち死亡件数: 1件(前年度比1件増加)
兼業・副業など複数の就業先での業務負荷が原因となる労災も発生しており、特に脳・心臓疾患における死亡件数の増加が懸念されます。
6. 裁量労働制対象者に関する労災補償状況
・脳・心臓疾患の支給決定件数: 4件(専門業務型3件、企画業務型1件)
・精神障害の支給決定件数: 4件(いずれも専門業務型)
裁量労働制下においても、過重な業務による健康障害が発生していることが確認されました。
7. まとめ
本報告書は、日本における「過労死等」の現状を数字で示しており、以下の重要な点を浮き彫りにしています。
過労死等全体の増加傾向: 請求、決定、支給決定件数すべてが増加しており、特に死亡・自殺(未遂含む)の支給決定件数が増えていることは憂慮すべき事態です。
人手不足の深刻な業界による、業務負荷からくるしわ寄せが、長時間労働やパワハラといった形で過労死(労災)として表面化している事が読み取れます。
脳・心臓疾患は長時間労働との関連が強い: 特に「運輸業、郵便業」の「道路貨物運送業」や「自動車運転従事者」において、月80時間を超える時間外労働が決定件数に最も寄与していることが確認されています。これは、特定の業種・職種における労働環境の改善が急務であることを示唆しています。
精神障害はハラスメントが主要因: 「医療、福祉」の「社会保険・社会福祉・介護事業」や「専門的・技術的職業従事者」、「一般事務従事者」で精神障害の請求・決定件数が多いです。
特に「上司等からのパワーハラスメント」が最も多くの支給決定につながっており、職場における人間関係や不適切な指導が大きなストレス源となっていることが明らかとなっています。
若年層における精神障害の増加: 精神障害では、40代が最多であるものの、20代~30代の若年層でも多くの支給決定がなされており、幅広い年代でのメンタルヘルス対策の重要性が示されます。
多様な働き方におけるリスク: 複数業務要因災害や裁量労働制においても労災が認定されており、働き方の多様化に伴う新たなリスクへの対応が求められます。
今回の報告内容から、改めて職場での過重労働やハラスメント防止に向けた労働環境の見直しが急務であることが浮き彫りとなっています。
■参考リンク
令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します(厚生労働省)
ご相談・お見積りは無料です
人事労務支援からコンサルティングのご相談まで、
どうぞお気軽にご連絡ください。